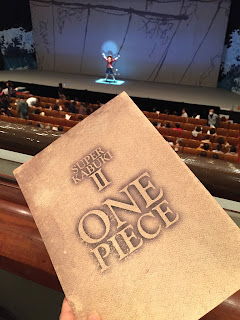中村壱太郎さんが総合演出をした、ART歌舞伎を繰り返しみて、久しぶりでブログ書きます。(汗)
ART歌舞伎は、コロナ禍中での日本のエンタメ系配信では群を抜いたクオリティの高さだと思いました。
(コロナ禍での配信でもう1つ素晴らしいと思ったのは、向井山朋子さんの「A Live」のシリーズですが、これは別の機会に)
で、
壱太郎さん(以下、壱さん)、ご自身のYouTobeチャンネルも始めたし、幸四郎さんの図夢歌舞伎にも付き合っていたし、じっとしていられなかったのでしょうね。
ライブ配信のアフタートークでプロデュサーの新羅慎二さんのコメントを受けて、壱さんが「何かやりたいとは思っていても、松竹さんから3密の関係で衣装やかつらなんかを借りるコトができなくて、新羅さんのお友だちのクリエーターに繋がっていった」というようなことをおしゃっていました。
そうなんだ、松竹が動かなかった(動けなかった)ことが、壱さんを歌舞伎の外側に放り出し、演出家としての才能を開花させることになったのか、そう思うと、コロナがくれた恩恵なのかもしれないです。新しいものが生み出される時というのは、そういう障害を乗り越えた先だったりするんだね。いえ、コロナはちっとも有り難くはないですが…
演奏家には、壱さんが選んで声をかけたそう。いつもの歌舞伎の舞台に立たないけど、伝統芸能に軸足を置きながら他ジャンルの音楽とも共演する機会の多い演奏家のみなさん。この劇伴チームの選定だけで壱さんのセンスの良さがわかる。音楽だけで公演をして欲しいくらいとても魅力的な演奏でした。推峰さん(お笛)は存じ上げていたけれど、山部泰嗣さん(太鼓)、中井智弥さんは初めて。すごいコラボでした。(中井さんのCDポチリました。)特に津軽三味線の浅野祥さんの抜擢は(仙台という贔屓目なしに)良かった。
踊り手と楽器を一対で構成した第一部「四神降臨」がカッコ良く終わって、場転、二部の「五穀豊穣」では三味線を脇に立てた浅野さんが舞台の中央で、民謡『豊年こいこい節』を独唱。ほわっと土の香りがしてくるようでした。滋味があり、こころに染みてくる歌声でした。お爺ちゃんが好きな歌だったのかな?
そして浅野さんと太鼓の山部泰嗣さんの「神狗」、伝統芸の超絶技巧を魅せていただきました。浅野さんの津軽三味線はキレの良さもあるけど繊細さが魅力なんですよね。
この演奏のあとで、第三部「祈望祭事」。
これが藁人間が三番叟を踊るという趣向。太鼓が「月」に見立てられておりました。
北国ではお馴染みの来訪神のイメージでしょうか、伴奏は津軽三味線だし。
でも、私が個人的に彷彿したのは、「荒神さん(こうずんさん)」。
いがらしみきお先生の強烈な作画が蘇ってしまった。…あのこうずんさんが、可愛く三番叟を踊っているってだけでストライク。
ちなみにいがらし先生の描かれた「こうずんさん」はこちらです。
Byせんだいメディアテーク「物語りのかたち」展より。
お芝居の「花のこゝろ」はもちろん良かった。凄いもの見た感。
右近さんは当世風の2枚目ですね。おばちゃんは、若い時はお姫様やっていたのにずいぶん芯が太くなったものだよねぇ…なんて思ってしまいましたが。
友吉鶴心さんの琵琶語りが、すんなり分かりやすく物語を伝えてくれました。
コロシ役のお二人、花柳源九郎さん、藤間涼太朗さんの存在感も大きい。舞踊家は自在なんだね。式神みたいでした。早乙女の七夕の吹き流しみたいな衣装も舞台に映えていました。
ART歌舞伎は、歌舞伎の寸法や枠組みからはみ出した、歌舞伎のエレメントが変異してスパークした作品という印象。
もちろん、衣装や化粧が全然違ってもいたし、映像(カメラ7台、リハなしの一発撮りらしいです。天才か!)や照明の効果も絶大だった。
若いチームだからこその、異種混交の型破り感と、それを成し遂げて新しい地平を見た青年達の高揚感が伝わって来て、見ているこちらまで幸せな気持ちになりました。とにかく楽しそうだった。あれは関わった人全員の肥やしになった作品だったのだろうと思います。